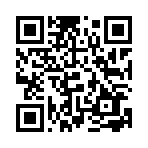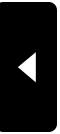2019年11月06日
めふんのメンミ漬け
鮭は捨てるところが無いと言う・・・
本当にそう思います。
今回、めふんのメンミ漬けを作ってみます!
もちろん初挑戦!
本当にそう思います。
今回、めふんのメンミ漬けを作ってみます!
もちろん初挑戦!
まず、めふんとは?
出典先:ウィキペディア (Wikipedia) より
めふんは、オスの鮭の中骨に沿って付いている血腸(腎臓)を使って作る塩辛である。
北海道の地方料理であり、料理店などでは珍味として扱われている。
スーパーマーケットや土産物店では、100g程度の瓶詰めとして流通している。
また、川を遡上中の「ぶなざけ」と呼ばれる鮭の腎臓が材料として良いとされる。
色は黒く、食感にとろみがあり、主に酒肴として珍重されているほか、
ストレスを回復させる栄養素であるビタミンB12や鉄分が豊富に含まれているため、
健康食品としても注目されている。
めふん(血合い)のメンミ漬けの作り方
【材料】
めふん(サケの血合い):3尾分(手に入る分)
塩:たくさん
メンミ(めんつゆもしくは醤油):めふんがひたひたに浸かる量
生姜(無い場合、チューブの生姜):1尾分3cm(好みで適量)
【作り方】
1.生サケの背骨(中骨)内側にある血合いを指を使って、丁寧にちぎれないように取る。

2.取った血合いの血抜きをするため氷水に浸します。

3.時間が経つと血が滲んでくるので、1時間ほど漬け、
様子を見ながら血が滲まないようになるまで、3回ぐらい取り替える。

4.その後、水を切ってボールの中でたっぷりの塩に漬け、冷蔵庫で一晩寝かせる。

5.一晩経って、塩を水で洗い流し、また氷水に入れて塩抜きをする。
(塩抜き時間は1時間程度、これを3回程度く繰り返します)

6.塩抜きしためふんの水気をキッチンペーパーを使い拭き取る。

7.水気が無くなっためふんをボールに戻し、

めふんを指でつまみ吊るしながら、キッチンバサミで食べやすい1cm程の長さに切る。

8.ボールの中でメンミにひたひたに浸かるようにして、さらに生姜を入れる。

9.今回はチューブ生姜を9cm程度入れ、冷蔵庫で3日ほど寝かせて完成です。

しっかりを血抜きをすれば、血生臭さはほとんどありません。
食感もやわらかいレバ刺しみたいな感じ~。
ご飯の上にのせて食べると美味しい~
1147
出典先:ウィキペディア (Wikipedia) より
めふんは、オスの鮭の中骨に沿って付いている血腸(腎臓)を使って作る塩辛である。
北海道の地方料理であり、料理店などでは珍味として扱われている。
スーパーマーケットや土産物店では、100g程度の瓶詰めとして流通している。
また、川を遡上中の「ぶなざけ」と呼ばれる鮭の腎臓が材料として良いとされる。
色は黒く、食感にとろみがあり、主に酒肴として珍重されているほか、
ストレスを回復させる栄養素であるビタミンB12や鉄分が豊富に含まれているため、
健康食品としても注目されている。
めふん(血合い)のメンミ漬けの作り方
【材料】
めふん(サケの血合い):3尾分(手に入る分)
塩:たくさん
メンミ(めんつゆもしくは醤油):めふんがひたひたに浸かる量
生姜(無い場合、チューブの生姜):1尾分3cm(好みで適量)
【作り方】
1.生サケの背骨(中骨)内側にある血合いを指を使って、丁寧にちぎれないように取る。
2.取った血合いの血抜きをするため氷水に浸します。
3.時間が経つと血が滲んでくるので、1時間ほど漬け、
様子を見ながら血が滲まないようになるまで、3回ぐらい取り替える。
4.その後、水を切ってボールの中でたっぷりの塩に漬け、冷蔵庫で一晩寝かせる。
5.一晩経って、塩を水で洗い流し、また氷水に入れて塩抜きをする。
(塩抜き時間は1時間程度、これを3回程度く繰り返します)
6.塩抜きしためふんの水気をキッチンペーパーを使い拭き取る。
7.水気が無くなっためふんをボールに戻し、
めふんを指でつまみ吊るしながら、キッチンバサミで食べやすい1cm程の長さに切る。
8.ボールの中でメンミにひたひたに浸かるようにして、さらに生姜を入れる。
9.今回はチューブ生姜を9cm程度入れ、冷蔵庫で3日ほど寝かせて完成です。
しっかりを血抜きをすれば、血生臭さはほとんどありません。
食感もやわらかいレバ刺しみたいな感じ~。
ご飯の上にのせて食べると美味しい~
1147
Posted by fumitatsuko at 06:00│Comments(0)
│料理
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。